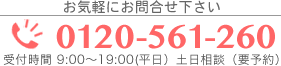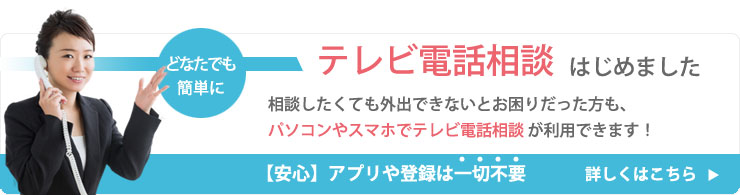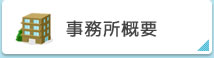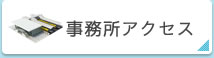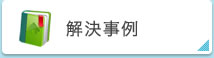3.改正相続法によって変更されたこと | 【特集】改正相続法
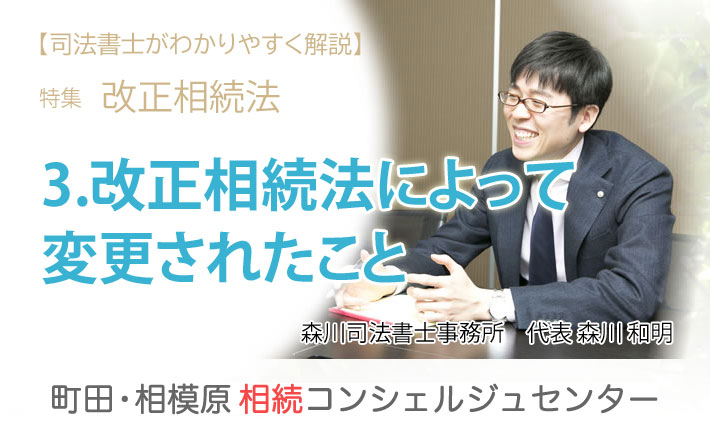
2018年7月、約40年振りに相続法が大きく改正されました。改正内容はすでに施行済です。
遺言執行者についても大きな改正があったので、正しい知識を持っておきましょう。主には「権限が強化、明確化」されたので、従来よりも遺言執行者の活用幅が大きくなっています。
以下で遺言執行者についての改正点をご紹介していきます。
3-1.遺言執行者の立場が明確にされた
1つ目は、遺言執行者の立場の明確化です。
改正前の民法では「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす」と規定されていました。ただ遺言執行者は相続人の意に反する行動をとることもあります。たとえば愛人へ遺贈する場合には、相続人から大きな反感を買うでしょう。
そういったとき、相続人が遺言執行者に対し「相続人の代理人なのに、私の不利益になる行動をとるのはどういうことか?」と言ってきてトラブルになるケースが多々ありました。
そこで改正法では、遺言執行者は相続人の代理人ではなく「遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と規定されました(民法1012条1項)。
- 民法1012条1項
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
つまり遺言執行者は単なる相続人の代理人ではなく「独立して遺言内容を実現できる権利を持つ」と明確化されたのです。今後は遺言執行者が相続人からクレームを受けて業務を行いづらくなるトラブルを避けやすくなるでしょう。
遺言執行者による行為の効力を明確化
改正民法は、遺言執行者が「遺言執行者である」と示して行った行為については相続人に対して直接効力を発生する、とも規定されています(民法1015条)。つまり遺言執行者が「私は遺言執行者としてこの手続きを行います」として遺言内容に即した行動をとったときには、その効果が当然に相続人に及ぶということです。
たとえば遺言執行者が預金の解約払戻を行うとき、相続人に「遺言執行者として預金の解約や払い戻しを行います」と告げて手続きをすれば、相続人は反対できません。
遺言執行者は相続人の希望に左右されず、遺言者の意思に従って遺言内容を実現できることが明らかになりました。
3-2.遺贈の履行は遺言執行者にしかできない
改正法により、遺贈がある場合の取扱いも変更されました。
遺贈とは、遺言書によって特定の人に財産を受け渡すことです。相続人だけではなく、相続人以外の第三者へも遺贈は可能です。
遺贈は相続人にとって不利益となるケースも少なくありません。遺言執行者がいないと相続人が積極的に遺贈を行わなかったり妨害したりする可能性が懸念されます。
そこで改正法により、「遺言執行者がいる場合、遺贈は遺言執行者にしかできない」とされました。
- 民法1012条2項
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
遺言執行者が選任されると、相続人が遺贈の手続きを進めることができません。必ず遺言執行者が遺贈を行わねばならないのです。実は従前からこういった取扱いになっていましたが、今回の法改正で明確化されたかたちになっています。
このことで、遺贈を巡る相続人と受遺者のトラブルを避けやすくなるでしょう。
なお遺言執行者がいないケースでは、相続人が遺贈を履行します。
3-3.預貯金の払い戻しや解約権限が明確化された
相続法改正によって、遺言執行者に「預貯金の解約払戻しの権限」が従前よりもわかりやすく認められました。
- 民法1014条3項
「特定財産承継遺言」とは、財産を特定して相続させる遺言です。「A銀行の預金を長男に相続させる」と指定されている場合などが該当します。
こういった遺言が遺されると、遺言執行者は当然に預貯金の払戻しの請求や預貯金の解約の手続きを行えます。遺言書に「遺言執行者に預金の解約、払い戻しの権限を付与する」と書かれていなくても、遺言執行者による権利行使が可能です。
遺言執行者に解約払戻の権限を与えないためには、あえて遺言書に「遺言執行者には解約払い戻しの権限を与えない」と書いておかねばなりません。
このように「特定財産承継遺言」によって預金の相続方法が指定されたとき、遺言執行者は当然に解約払戻できる権限が明らかにされました。
- 預金の一部を相続させる遺言の場合
「長男にA銀行預金のうち500万円を相続させる」など預金の一部を相続させる遺言があった場合には、遺言執行者の権利が及ぶのは指定された一部のみです。そこで500万円分のみ払い戻して長男に渡す権限が認められます。
預金以外については権限が認められない可能性がある
遺言執行者に解約・払戻しの権限が当然に認められるのは、基本的に「預貯金債権」のみです。株式や投資信託などの権利は対象外となっているので注意しましょう。
また特定財産承継ではない「相続分の指定」や「遺贈」をする場合、当然には解約権限が認められません。
株式など預金以外の財産や特定財産承継以外の場合に遺言執行者に解約権限を与えるには、基本的に遺言書に「〇〇の株式について遺言執行者へ名義変更や解約の権限を与える」などと明確に記載しておくべきと考えられます。相続開始後にトラブルにならないため、遺言書作成の際には遺言執行者の権限を明確にしておきましょう。
3-4.不動産相続の場合にも単独で手続きできるようになった
今回の法改正により、遺言執行者は不動産相続の場合にも単独で名義変更の登記申請できるようになりました。
実は法改正前は遺言執行者が単独で名義変更できず、相続人による協力が必要でした。
たとえば父親が遺言書で「自宅を長男に相続させる」と指定しても、遺言執行者が単独で相続登記できなかったのです。登記は基本的に「自宅を相続する長男本人が行わねばならない」と理解されていました。
「なぜ遺言執行者が相続登記できないのか?」と不思議に思うかもしれません。
それは「相続が発生すると、死亡と同時に相続人が当然に不動産の所有権を受け継ぐので、遺言執行者が関与する余地がない」ためです。
遺言執行をしなくても当然に不動産の所有権は長男のものになるので、わざわざ遺言執行者が手続きする必要はない、と理解されていました。
最高裁がこういった考え方を採用していたので、「不動産を特定の相続人に承継させる」という遺言書があると、遺言執行者がいても相続手続きできないことが問題となっていました(最判平成7年1月24日、最判平成11年12月16日)。
そこで改正法は、不動産の特定承継のケースであっても遺言執行者が単独で相続登記できることにし、従来の取扱いを変更しました。
- 民法1014条2項
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共有相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
今回の法改正により「自宅を長男に相続させる」という遺言が残された場合、長男が自分で手続きをしなくても遺言執行者が単独で相続登記できるようになり、便利になったといえるでしょう。
なお法改正があっても相続人本人による相続登記ができなくなったわけではありません。相続人本人が自分で手続きをしても問題ありません。
3-5.遺言執行妨害行為が無効であることを確認された
今回の相続法改正により、相続人が遺言執行者の業務遂行を妨害したとき、妨害行為が無効となることが確認されました。
法改正前の規定内容と問題点
実は改正前の民法でも「相続人が遺言執行を妨害してはならない」という規定がおかれていました。ただ「妨害行為が無効になる」とまでは定められていませんでした。これでは妨害行為が行われたとき、その効果が発生するのかどうかがわかりません。そこで判例により「相続人による遺言執行者への妨害行為は無効になる」と判断され、その判断に従った運用が行われていました(大判昭和5年6月16日、最判昭和62年4月23日)。
たとえば遺言執行者が長男へ相続登記する前に他の相続人が不動産を売ってしまったとき、不動産の売却は無効となります。
判例の解釈によると、妨害行為が行われて善意の第三者が財産を取得したときにその財産はどうなるのかが問題です。確かに妨害行為は無効となりますが、買主に過失がなかった場合に不動産を取得できないと、買主は不当な不利益を受けてしまうでしょう。
改正法は善意の第三者を保護
そこで改正法は、遺言執行の妨害行為と第三者の権利を調整するため、以下のような規定を定めました。
- 民法1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
つまり、遺言執行者の業務に反する妨害行為は基本的に無効としながらも、事情を知らない第三者があらわれたときには「無効です」と主張できないことになりました。
善意の第三者の具体例
たとえば「長男に自宅を相続させる」という遺言があるとき、次男が遺言執行者を無視して不動産をAさんに売ってしまったとしましょう。
- Aさんが悪意の場合
Aさんが「次男は無権利で不動産を売った」と知っていれば売買は無効になります。 - Aさんが善意の場合
一方Aさんが「次男には権利がある」と思っていた場合、長男や次男はAさんへ「売買契約の無効」を主張できず、不動産はAさんのものとなります。
このように、改正法では遺言執行者の権限を強化しつつも事情を知らない第三者の利益も守るため、調整をしたといえるでしょう。
3-6.遺言執行者の通知義務
これまで、遺言執行者が就任したとしても、相続人へ通知しなければならない義務はありませんでした。しかし、それでは相続人としては遺言執行者がいるのかいないのかわからず、立場が不安定になってしまいます。
そこで改正法では、遺言執行者が就任すると「遅滞なく相続人に対して通知をしなければならない」と規定されました。
- 民法1007条2項
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
通知が行われたら、相続人は遺言執行者の存在を認識できるので、状況に応じた対応をとれるでしょう。知らず知らずの間に遺言執行者の行為を妨害してしまう危険も発生しません。
なおこの規定が直接的に適用されるのは「相続人」のみであり、受遺者へは通知の必要がありません。とはいえ現実的には遺言執行の手続きをスムーズに進めるため、受遺者へも通知を行う方が良いでしょう。
3-7.遺言執行者に関する改正法の施行時期、適用時期
遺言執行者に関する改正法の施行時期については非常にわかりづらくなっています。
正しく把握しましょう。
施行日
改正法の施行日は2019年7月1日です。
施行日以降に遺言執行者が就任したときに適用される改正内容
施行日である2019年7月1日以降に「遺言執行者が就任」したときに適用される改正内容は、以下の2つです。
- 遺言執行者の通知義務
2019年7月1日以降に遺言執行者に就任した人は、遅滞なく相続人へ遺言執行者に就任した事実を伝えなければなりません。 - 遺言執行者の権限
2019年7月1日以降に遺言執行者が就任すると、遺言執行者は「相続人の代理人」ではなく独立した立場で遺言執行の手続を行えます。
遺言書作成時期や死亡時期が2019年7月1日より前であっても、遺言執行者の就任時期が2019年7月1日以降であれば、上記の改正点が適用されます。
施行日以降に遺言書が作成されたときに適用される改正内容
以下の改正内容については2019年7月1日以降に遺言書が作成されたときに適用されます。2019年7月1日以前に遺言書が作成された場合や2019年7月1日以前に遺言者が死亡した場合、適用対象外となるので注意しましょう。
- 特定財産承継遺言についての事項
2019年7月1日以降に書かれた遺言書にしか適用されないのは「特定財産承継遺言」についての改正内容です。
具体的には「預貯金の解約払戻権限」と「不動産の相続登記の権限」です。
1.遺言執行者がいると、遺言書で「遺言執行者に預貯金の解約払戻権限を与える」と書かれていなくても、当然に遺言執行者が預貯金を解約、払い戻しできます。
2.不動産の相続が指定されていたときには、相続人の協力がなくても遺言執行者が単独で相続登記できます。
この規定が適用されるのは「遺言者が2019年7月1日以降に遺言書を作成し、死亡した場合」に限られます。古い日付の遺言書では、遺言執行者が単独で相続登記できず、相続人に協力を求めなければなりません。特定財産の承継を指定しているにもかかわらず現時点で「2019年7月1日以前」の遺言書しかない方は、遺言書を作り直した方が良いでしょう。
遺言書を作成し直した方が良いのか自分で判断しにくい方は、お気軽に司法書士までご相談ください。
改正相続法の最新記事
新着情報・解決事例・お客様の声
- 2025年12月8日解決事例
- 2025年12月8日解決事例
- 2025年12月8日解決事例
- 2025年7月18日解決事例
- 2025年7月18日解決事例
- 2025年5月28日生存贈与
- 2025年4月27日解決事例
- 2025年4月17日解決事例
- 2025年4月7日解決事例
- 2025年3月27日解決事例